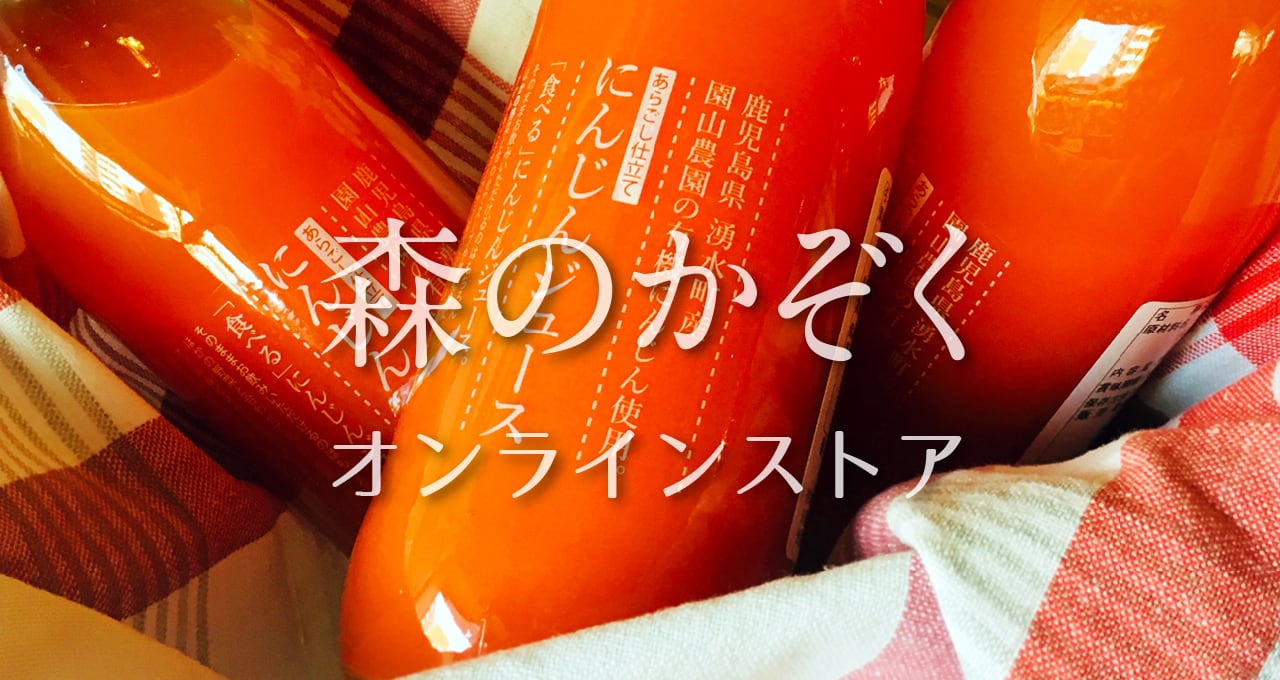2021/03/02 12:02

生産部長 園山秀国に聞く

たとえば、キャベツを例にすると、一般的な作り方では、大体9月に種まきして、11月に定植して、遅くまでおいておける品種を使って、4月までそれを引っ張るという作り方。だから、8か月かけて、4月に持ってくるやり方があるようです。
うちの場合は11月に種をまき、トンネルで急がせる。4月まででいうと、6か月。2カ月間をぎゅっと短縮して、なるべく早く仕上がってもらうような作り方をしてますね。トンネルを使わないと、冬の間気温がつくれないから、そうやって急がせるんです。
4月って、菜花も全部花を咲かせるし、大根も花咲かせるし、商品がなくなっちゃうんですよ。だから春に持ってくるためには、ちょっと変わったことしなきゃいけないかなということで、こういうやり方を今やっています。
4月は出荷するものがなくなっちゃう時期なので、そこにぴたりと合わせて作るようにしています。
今年、1年目なのですが、去年も作ったら、キャベツの仕上がりが5・6月になっちゃったんですよ。そしたらもう、別の品目とがっちゃんこするじゃないですか。だからなんとしても、急がないといけないということですよね。
経験のなせる技なんですね。
近くで似たようなことしてる人がいれば参考になるんだけど、参考になるデータがあんまりないので、ほかの地域から情報を引っ張ってきて、じゃあうちではどうなるかなみたいなことを考えてやってますね。
今出荷しているのが、いくつかな、にんじん、ほうれん草、じゃがいも、だいこん、キャベツ、白菜、この時期は6~7種類ありますかね。わりと多い時期ですね。もうほんと、ごぼうしかないとかね、そういう時期もあるんですよね。
お野菜、本当にどれもおいしいです。
なんか有機のよさが出る品目っていくつかありますよね。キャベツもそうですし、ほうれん草とか、通常えぐみを感じるような野菜でも、すっきり甘かったりすると全然違うし、じゃがいもも、ここ何シーズンかは、非常に良いものができていて、お客さんの反応も良いものが結構でていますね。「甘くておいしい」っていう風に。

違いはどこからくるものなのでしょうか。
一般栽培とちがうのは、土の違いですね。土を作るほど、おひさまからと地面からとで、同じ甘味成分が同時に、二方向から作られるんです。土を作っていないと、おひさまからだけだから、そういう意味では土を作っていない畑よりも、2倍の甘さの野菜ができるというところがありますよね。やっぱり食べて違いがわかるようなもの作っていかないと、安全だけじゃ、なかなか。
健康な土づくりというところが一番の違いになるんですね。
お客様からは、「なんかわからないけれど、おいしい」と感じていただけるのだけでいいと思うんです。
おいしい野菜のための土づくりってどういうことをするんでしょうか。
簡単に言おうとすると、微生物を、いい微生物を育てながら炭水化物をいっぱい入れていくっていうことになるんですよ。
炭水化物っていうのが、いわゆる堆肥入れたり、緑肥っていって草を敷きこんだりする土づくりっていうことですね。それをする過程で、微生物が乱れがちになって、病気がでちゃったりすることがあるので、微生物も、いい微生物を養うようにしています。
同時並行でこの二つをやっていくってことになるんですよね、土づくりっていうのは。
どっちかでもいけないし、僕もどっちかだけ意識していて、片方のことで転んだりということが結構あって、ようやく今、この2つは平行してやるんだなっていうことがわかってきたくらいです。
それができれば、病気が少なくて、甘くておいしい野菜がとれるようになるということなんです。
炭水化物っていうと、パンとかごはんとかっていうイメージあるじゃないですか。糖分につながっていきますね。
糖分や、ビタミンCや、繊維や、これが全部炭水化物なんです。同じ元素なんだけど、組み合わせが違うだけ。
だから炭水化物っていうのは、それこそ光合成で葉っぱで作られてるのが炭水化物。
作物の中で、甘みにもなるし、ビタミンにもなるし、繊維づくりも。
ごぼうとか、ああいうのは全部、まずは光合成で作られているということになるんですね。
だから、豊富であればあるほど、甘くて丈夫で、甘さと酸っぱさとちょうどいい作物ができるっていうことなんですね。だからそれをその、今は光合成の話だったけど、地面から吸わせようとすれば、こういう草を堆肥として使っていくわけです。
この中には糖分もあって、ビタミンもあって、炭水化物がいろんな形でここに入ってるわけですよ。
それをもっと大量に、ドカッと入れてやる。入れれば入れるほど、下から入る炭水化物がたくさん用意できるということなんですね。
こういうものを堆肥とかという形で入れると、必ずこれを分解していた微生物のことを考えなくてはいけない。
そこには善玉と悪玉といるんです。なるべく善玉に分解してもらう。
で、微生物が元気なうちに、畑に入れてやると、畑の中に善玉の微生物が増えていって、この大量の炭水化物を、善玉が活躍しながら分解していってくれるわけですよ。
そうすると、病害が減ってですね、なおかつ、下からぐっと吸える炭水化物も増える。
で、今堆肥を作り始めてるんですけど、今まで「緑肥」と言って、牧草で炭水化物供給をしてたんだけど、それを分解しようとする菌を入れてなかった。
微生物のことが頭になかったので、土の中にいる微生物が普通に分解してくれるから、そこまで意識してなかったんだけれども、やっぱり病害がでちゃうんですよね。やっぱりこいつらをおさえなくてはいけないと。
善玉増えてもらわなくては、というのをやっぱり考えてないと、ただこういう草を入れていくだけでは、自由な、野放しに分解を始めるから、こういう善玉に分解してほしいっていう意図的なことをやんないといけないわけですね。
だからどうしても、自分の管理下で、いい発酵をさせて、いい微生物をわかした堆肥がどうしても必要になるなと至っているということですね。だから草堆肥がうまく動くようになれば、かなりの問題が解決されるんです。
おいしい野菜が作られているのは、土づくりはもちろん、良質の草堆肥が関係しているんですね。

このほかにも、生産部長園山には野菜作りの展望についても話をしてもらいました!それはまた今後!
太陽や土、微生物など、自然の力をめいっぱいいただきながら、そのやま農園では土を作り、有機の野菜を作っています。
有機野菜を中心に、ひとりでも多くの方においしく健康な食べ物をお楽しみいただきたい。
そんな思いでスタッフ一同、今日もお客様をお待ちしています。